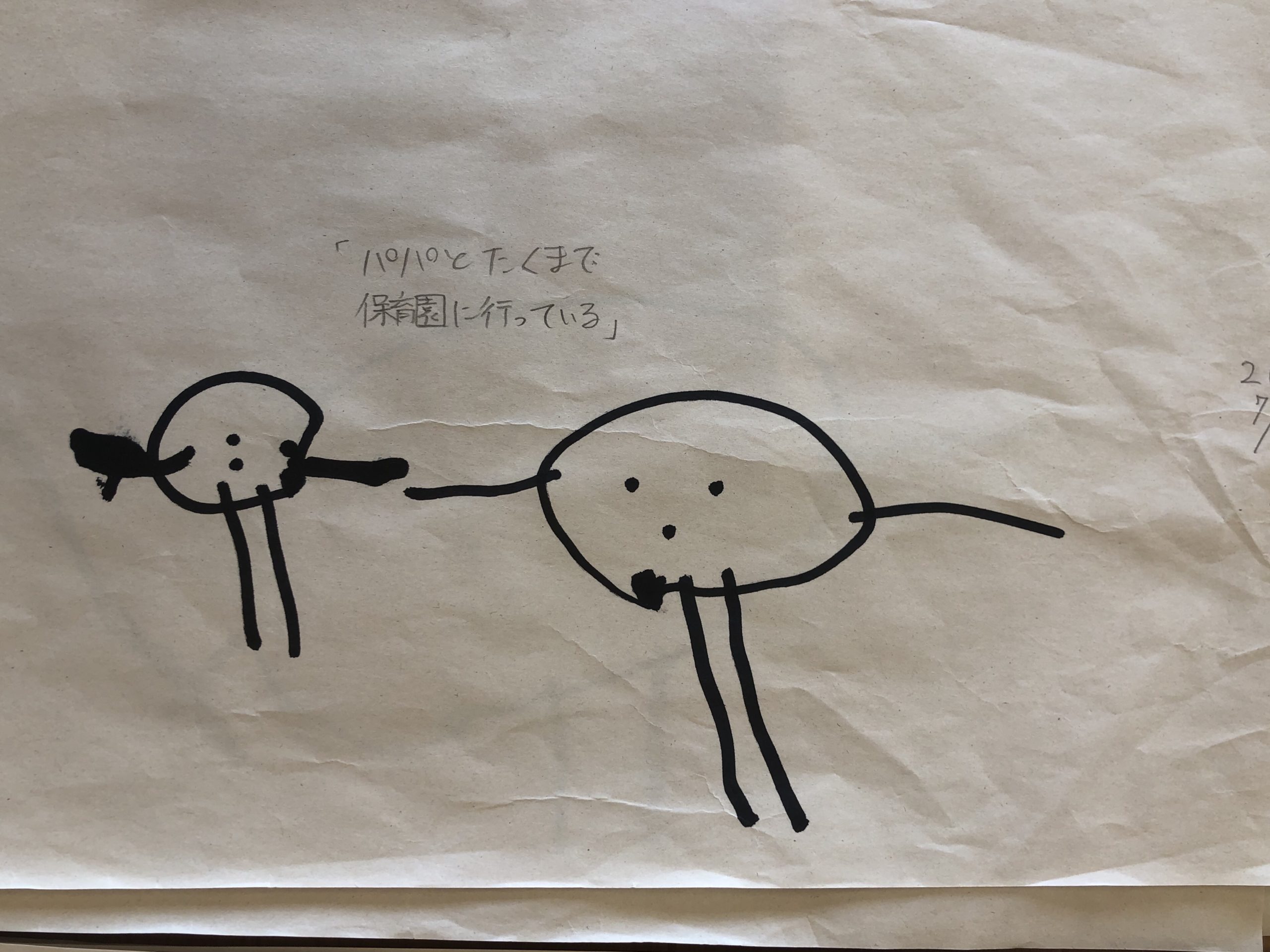1、さくらさくらんぼ保育
昨年2019年4月に開園した、こばとゆがふ保育園。沖縄県中頭郡西原町に新設された認可保育園だ。
前身は、無認可保育園のこばと保育園。娘も息子も生後2ヶ月〜4ヶ月から入園していて、昨年4月にゆがふの方へ移行した。
斎藤公子さんが創り出した「さくらさくらんぼ保育」という保育を実践していて、0歳から小学生に上がる前、人間を科学的発達からの保育を実践している。
▼さくらさくらんほ保育
https://www.y-oohashi.com/斎藤公子メソッド/
https://note.com/saitouhoiku1920/n/n9fdbe84d8a8d
0歳児のからだを揺らし血流を良くして、脳への刺激を与える。サルと構造が異なる「足の親指」は、二足歩行や進化していく人間の特徴。だ
その足の親指をしっかりと使うことで、脳の発達をうながす。生物の進化と同じ進化の過程の動きをする「リズム」は見事だ。
▼両生類のハイハイ
2、障害児もみんな一緒の統合保育
こばと保育園でもゆがふでも、感激するのは、障害を持って生まれてきた子どもも、健常児と一緒に保育を受ける統合保育。
生まれた時、脳が半分しかなかった子ども。低体重で脳から血がでていた子ども。ダウン症、知的障害、身体障害。
そんな障害を持って生まれた輝く魂をもった子どもたちも、みんな一緒に保育園で遊んだり、絵を書いたり、リズムをする。
夏祭りも運動会も、みーんな一緒の演目をする。例えば、縄跳びは、年長になったら自分たちで編んで、それを跳んで走るリズムをするんだけど、
障害をもってて編むのが難しい子は、短いのを2つ編んで、運動会では、縄跳びを跳んで園庭をかけるんじゃなく、両手でブンブン振り回してその子どものペースで走ったり歩いたりする。
跳び箱だって、飛ばなくても跨いで飛び越えたらいいし、そう、それぞれができるように工夫して、みんな同じ演目をやるの。
それをみんなでサポートして、みんなで応援する。バカにしたり、それを、変だと思う子なんて1人もいない。そういう違いをみんな不思議とも思わず、それが個性だと認め合っている姿にいつも感動する。
さくらさくらんぼ保育では、本物に触れて、本物を聴いて、本物を食べて育つ。おむつは紙おむつじゃなく布おむつとパンツ。リズムはグランドピアノの伴奏で、テレビNG。お弁当はプラスチックもNG。
それで、出生時に脳出血を起こした子の発達も健常児と変わらなく追いつき、アトピー、喘息も治っちゃうんだから。障害あるなし(まぁ、私も含め障害はみんな持ってると思うんだけど)関係なく、子どもたちの健やかなる育みに良いことは、納得する。
3、65歳オーバーのレジェンドがズバリ!絵の学習会
去年開園して、今年がコロナで、一年半ぶりの学習会。
認可園になって、これら独自の教育を町の方針とは反していて、町との折り合いというか、話し合いが大変だと園長が話す。
それを踏まえて、色々とこれまで伝えたい思いを伝えられず、うっぷん?が溜まってたんだろう。
一人一人の園児の絵をみながら、解説していくんだけどさ、65歳園長と0歳児のスペシャリスト70歳代?のレジェンドが、遠慮なく、ズバズバっと保護者にアドバイスするのが痛感だった!
「この絵は寂しがってますね。下のお子さんができたころから、塗り潰しの絵があり、内面を潜めて我慢してる第一子の様子がわかります。
嫉妬は、人をも殺すくらいのエネルギー。まず第一子から抱きしめてあげて。」
「テレビをみて、早期文字教育は害。まずからだと心を、五感を自然の中で豊かに育み、その上で、学びたい意欲や学ぶ座れる体になる。学ぶのはその後からで十分追いつき、追い越してしまう。」
「他の教育を否定しているのではなく、さまざまな状態の子供たちも受容していきたい。子どもたちは素晴らしいから。でも、テレビを見せたり、早期教育は本当に考えてほしい。」
本当に子どもたちに良い環境、良い人生の土台をつくりたいんだって伝わる、温かいからこそ言い切るかっこよさを私は感じた。
久しぶりに、園長と保育士の想いをきけて、私の気持ちも爽快だった。
わざわざ、このこばと保育園(いま、ゆがふ)に入るために県外から引っ越してきた家族もいる。
息子の担任は、東京の保育士をしてたのに、わざわざ、斎藤公子さんの保育で全国一番といわれている沖縄のこの保育園を希望して移住してきた。
担任が、「園に疑問や違和感があったら言ってきて欲しい。子どもたちのために親と保育園、私たちが本気で話しあっていきましょう。苦情、意見ウェルカムです。」
とくくった。
保育園で、そりゃ自分の考えとは違い、疑問に思うことはある。保育園に限らず、世の中そういうもんだし、いちいち気にすることは否定して小さい人間なのかなと思ってた。だから、別に意見することも、疑問をぶつけることもなかった。
でも、自分の疑問は置き去りにせず、やっぱり伝えようと思った。自分の気持ちをおざなりにしていたら、子どもたちもそうなる。
4、うちの息子たくまくん発達と、母の私との関係。
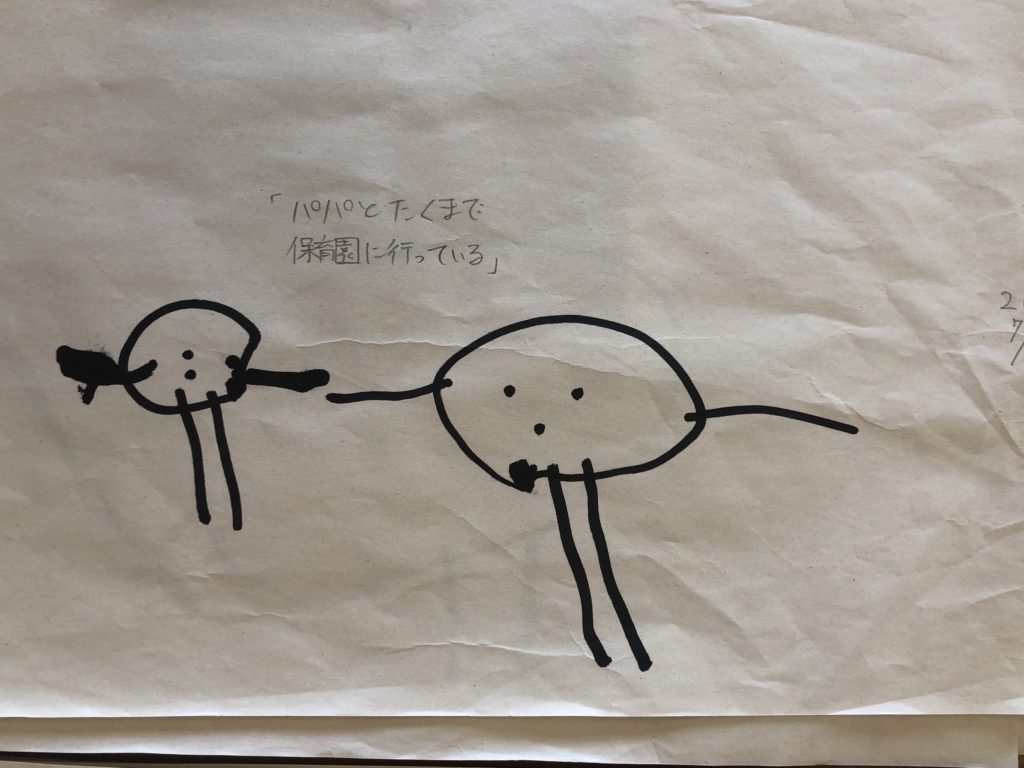
息子の絵は、まだ胴体の認識、地上の認識がない。同年代よりも認識が遅いみたい。そして、お友達のとの絵が少なく、1人の絵も多い。
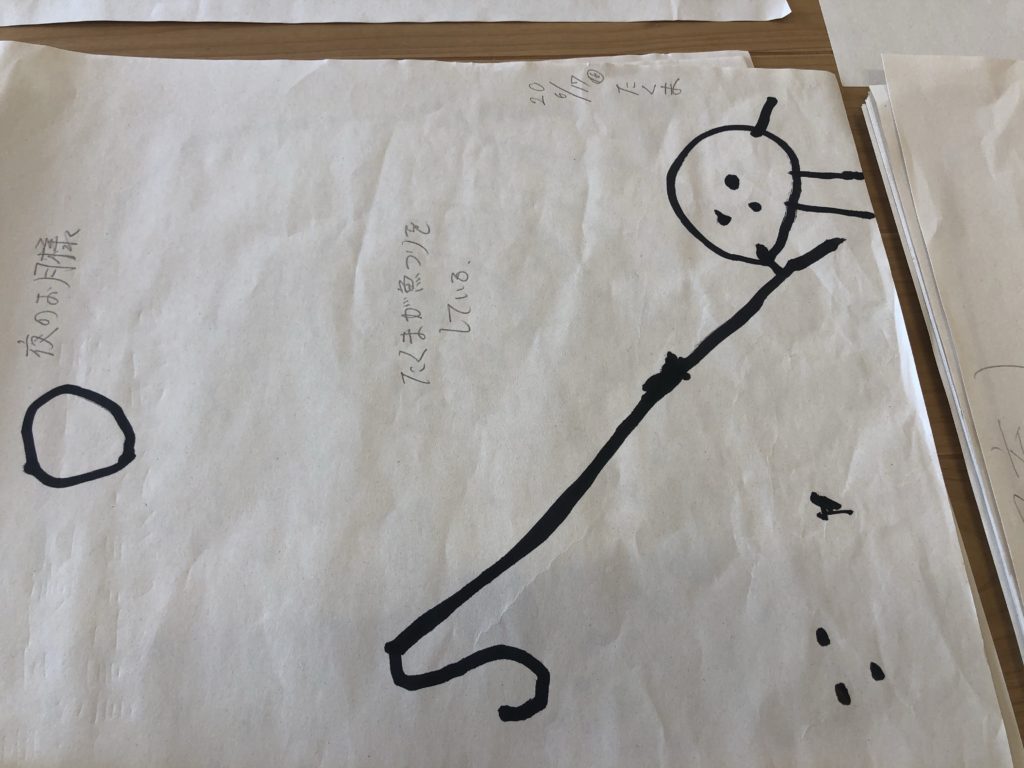
学習会で、担任と話していて、気付いた。
たくまは、なんでお母さんのお腹にきたのか?きくと、「天から私を助けにきた」と言っている。
たくまは私の気持ちに敏感で、今日の学習会でもあったが、幼児期は親の内面をも模倣する。
母の私を助けるため、たくまはわたしを元気付けたり、いつも優しく寄り添ってくれる。
たくまは、私の気持ちに癒着してるともいえる。お母さんである私がたくまが寄り添わなくても幸せであったなら、たくまは、安心して、自分からもっと外へ出て、友達と過ごし、自分の意思で行動するだろう。
担任の先生と話してて、「お母さんはお母さんの幸せに集中することですね。」という結論?に至って納得した。
担任と親とが、絵一枚から発達を想像して、内面をも理解していく、このプロセスも、とても豊かな時間だった。
言いたいこといって、好きに表現がして、自分を幸せにしてあげよ。

ってことで、保護者会終わったあとは、夫の運転で、夫のおごりで、ビールと中華♡しあわせ♡
沖縄に嫁に来て9年目、2児の母。沖縄でシュタイナー学校設立準備中。詳しくはこちら